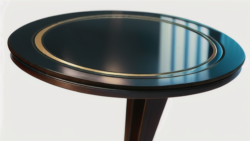年金
年金 過去勤務債務とその影響
過去勤務債務とは、企業が従業員に約束した退職後の給付に関わるもので、制度を新しく作った時や内容を変えた時に発生するものです。簡単に言うと、従業員が制度開始前や変更前に働いていた期間に対応する年金の支払いに必要なお金が足りないということです。
従業員は会社で働くことで将来、退職金や年金を受け取る権利を得ます。企業は従業員が安心して働けるよう、退職後の生活を保障する制度を設けていますが、この制度を新しく導入したり、あるいは内容を充実させたりする場合、過去に働いていた期間についても年金を支払う約束をすることがあります。この時、約束した年金を支払うのに必要な金額と、実際に準備できているお金の差が過去勤務債務となります。
例えば、ある会社が新しく年金制度を作ったとします。この会社で10年間働いている従業員Aさんは、制度開始前の10年間についても年金を受け取ることになります。この10年間分の年金支払いに必要な金額が、過去勤務債務として計上されるのです。不足額が大きいほど、会社の財務状態に与える影響も大きくなります。
過去勤務債務の計算方法は、厚生年金基金と確定給付企業年金で少し違います。厚生年金基金の場合は、将来支払う年金の今の価値で計算した「数理債務」と、法律で定められた最低限積み立てておくべき「最低責任準備金」を合計した金額から、実際に持っている年金資産のお金を引いた金額が過去勤務債務です。一方、確定給付企業年金の場合は、「数理債務」から年金資産を差し引いて計算します。どちらの場合も、将来の年金支払いを確実にするために、企業は計画的に積み立てを行い、財務の健全性を保つ必要があります。