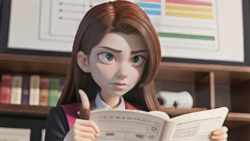指標
指標 国内総生産:経済の健康診断
国内総生産(GDP)とは、ある一定の期間、普通は一年間に、国の内で新しく生み出された、すべての財やサービスの合計額のことを指します。これは、国の経済の規模を表すとても大切な指標であり、例えるなら経済の健康状態を測る体温計のようなものです。
GDPは、国内で作り出された価値の合計なので、海外で生産されたものは含まれません。具体的に言うと、工場で製品を作る活動や、農家がお米を作る活動、会社が提供するサービス、政府が行う公共サービス、例えば道路の整備や学校の運営なども含まれます。また、家計で行う消費活動、例えば洋服を買ったり、ご飯を食べに行ったりすることも含まれます。
GDPは、生産、分配、支出という三つの側面から計算することができます。生産の側面からは、各産業が生み出した付加価値の合計として計算されます。付加価値とは、生産活動によって新たに付け加えられた価値のことです。分配の側面からは、生産活動によって生み出された所得の合計として計算されます。支出の側面からは、財やサービスの購入に使われた支出の合計として計算されます。どの側面から計算しても、同じ値になります。
GDPが増えている場合は、経済が成長していることを示し、反対にGDPが減っている場合は、経済が縮小していることを示します。GDPの成長は、雇用の増加や賃金の上昇につながり、人々の生活水準の向上に貢献します。逆に、GDPの減少は、失業の増加や賃金の低下につながり、人々の生活に悪影響を及ぼします。
GDPを理解することは、経済の動きを掴み、将来の投資判断を行う上で非常に大切です。GDPの動向を注視することで、景気の良し悪しを判断し、適切な投資戦略を立てることができます。また、他の国と比べてGDPの規模や成長率を比較することで、世界経済におけるその国の位置づけを理解することもできます。