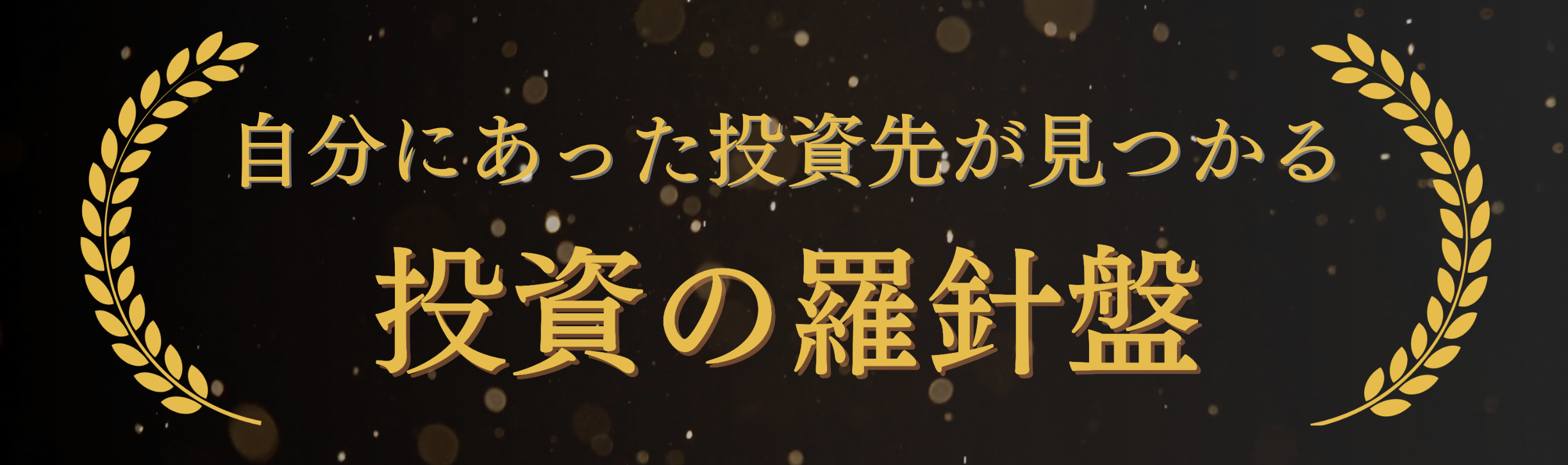経済知識
経済知識 供給サイド経済学:経済成長の鍵
供給サイド経済学とは、経済を果樹園に例えると、より多くの果物を得るために、果物を買わせるのではなく、木を育てて実を多くつけるようにすることです。つまり、モノやサービスの供給能力を向上させることで経済成長を目指します。従来の経済学は、需要、つまりモノやサービスを買う力を高めることで景気を刺激しようとしてきました。たとえば、お金をたくさん刷って人々に配れば、人々はたくさんモノを買えるようになり、経済が活発になる、という考え方です。しかし、供給サイド経済学は、この考え方に疑問を投げかけました。
供給サイド経済学は、モノやサービスを作る側の能力、つまり供給能力が経済成長の鍵だと考えます。いくら人々がお金を持っていても、買うものがない、または少ないと、経済は活性化しません。むしろ、物価が上がってしまい、生活が苦しくなることもあります。ですから、供給サイド経済学では、企業がより多くのモノやサービスを作れるようにすることが重要だと考えます。
具体的には、減税や規制緩和といった政策が有効だと考えられています。税金を下げれば、企業はより多くの利益を得て、設備投資や研究開発に回せるようになります。また、規制が緩和されれば、新しい事業を始めやすくなり、より多くのモノやサービスが生まれる可能性が高まります。これらの政策によって、企業の生産意欲を高め、供給能力を向上させることが期待されます。
この考え方は、フェルドシュタインやラッファーといった経済学者たちによって提唱されました。「供給重視の経済学」とも呼ばれています。彼らは、需要を刺激する従来の政策では、長期的には経済成長につながらないと主張し、供給能力を高めることの重要性を訴えました。供給サイド経済学は、革新的な考え方として注目を集め、その後の経済政策にも大きな影響を与えました。まるで、果樹園でより多くの果物を収穫するために、木をより健康に育て、より多くの果実を実らせることに注力するようなものです。そして、たくさんの果物が実れば、自然と人々はそれを求めて買うようになり、経済は活性化していくと考えます。