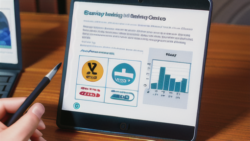 株式投資
株式投資 持ち合い株の功罪
持ち合い株とは、複数の会社がお互いの株を持ち合う状態のことを指します。会社同士が株を保有し合うことで、安定した株主関係を築き、経営の安定化を図ることを目的としています。これは、長年にわたり日本の会社社会で広く見られる慣習でした。
例えば、自動車を作る会社とその部品を作る会社を考えてみましょう。自動車を作る会社が部品を作る会社の株を持ち、同時に部品を作る会社も自動車を作る会社の株を持つことで、両社は安定した取引関係を築くことができます。自動車を作る会社は必要な部品を安定して調達でき、部品を作る会社は安定した販売先を確保できるというわけです。これは両社にとって大きな利益となります。さらに、持ち合い株には、他の会社から一方的に株を買われて経営を乗っ取られることを防ぐ効果もあります。多くの株を保有する会社が味方であれば、乗っ取りを企てる会社は簡単に過半数の株を集めることができません。
しかし、近年は持ち合い株の利点と欠点が改めて議論されるようになっています。持ち合い株は会社の経営を安定させる反面、会社の成長を阻害する可能性も指摘されています。持ち合い株によって安定した経営環境が得られると、会社は新たな挑戦をしにくくなり、変化への対応が遅れる可能性があります。また、本来は経営状態が悪くても、持ち合い株によって守られているため、実態以上に会社の価値が高く評価されてしまうこともあります。
このように、持ち合い株には利点と欠点の両方があります。それぞれの会社は、自社の状況や将来の展望を慎重に検討し、持ち合い株を保有するかどうかを判断する必要があります。





